2025.10.27
雨漏りリスクを最小限に抑える:建物の構造と設計のポイント
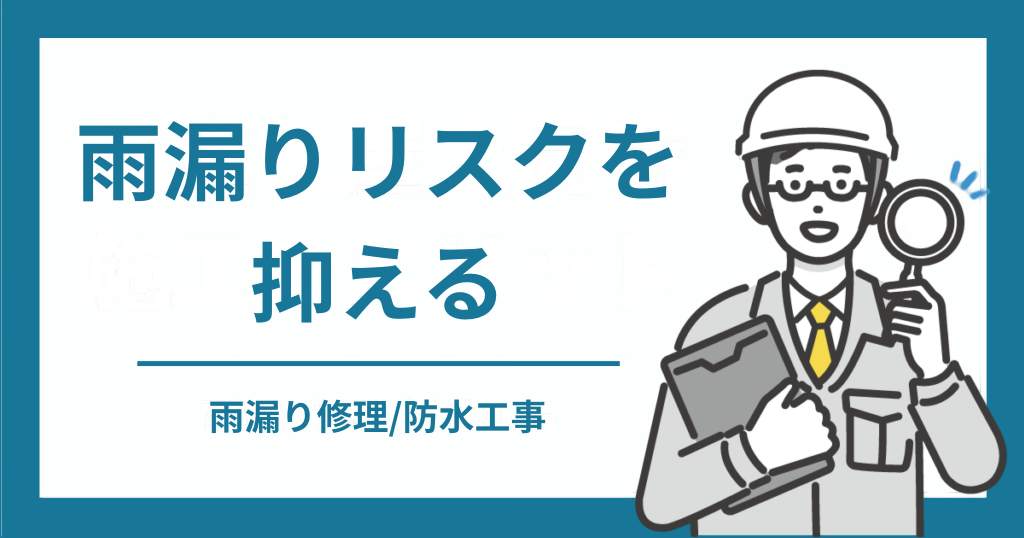
建物の経年劣化と共に発生しうる雨漏りは、できる限り避けたいトラブルの一つです。雨漏りは、建物の構造を傷めるだけでなく、カビの発生による健康被害や、企業の施設であれば業務への支障、資産価値の低下といった様々な問題を引き起こします。
本コラムでは、どのような条件の建物が雨漏りしにくいのか、雨漏りリスクを低減するための設計や素材のポイントについてご紹介します。これは、新築を計画されている個人のお客様だけでなく、既存の建物の改修や長期修繕計画を検討されている法人のお客様にとっても重要な情報となるでしょう。
雨漏りしにくい建物の条件①:屋根の形状がシンプルであること
雨漏りは建物の様々な箇所で発生しますが、特に屋根は雨水を直接受け止める最上部の構造であり、その形状は雨漏りリスクに大きく影響します。屋根を構成する各部位のつなぎ目や接合部は、雨漏りの原因となりやすい場所の一つです。
一般的に、屋根の構造が単純で継ぎ目が少ないほど、雨漏りしにくいとされています。逆に、継ぎ目が多く複雑な構造の屋根は、水の浸入経路が増えるため、雨漏りのリスクが高まります。
さらに、屋根の勾配(傾斜)も雨漏りのリスクに影響します。屋根の勾配が緩やかな場合、雨水が滞留しやすくなったり、強風によって雨水が屋根材の下に逆流したりする「吹き込み」や「逆流現象」が起こる可能性が高くなるため、雨漏りのリスクが増大します。
雨漏りしにくい屋根の形状
では、具体的にどのような屋根の形状が雨漏りしにくいとされているのでしょうか。ここでは、代表的な「切妻屋根」「寄棟屋根」「方形屋根」をご紹介します。
- 切妻(きりづま)屋根 「切妻屋根」は、屋根の最も高い部分(大棟)から左右に2つの傾斜面が地面に向かって伸びたような、非常にシンプルな形状をしています。このシンプルさゆえに、継ぎ目の数が少なく、雨漏りしにくいという大きな特徴があります。 また、雪が積もった場合でも、屋根から雪が落ちる場所を予測しやすいため、積雪の多い地域で一般的に採用されています。構造が単純なため、もし雨漏りが発生するとすれば、屋根の頂上部である大棟の部分に原因が限定されることが多く、他の複雑な形状の屋根に比べてメンテナンスも比較的安価に済ませられるのが特徴です。
- 寄棟(よせむね)屋根・方形(ほうぎょう)屋根 「寄棟屋根」や「方形屋根」は、屋根の全ての面が4方向に傾斜している屋根です(方形屋根は四面が同じ形)。この形状により、雨を多方向に効率よく分散させることができるため、他の屋根形状と比較して、屋根材への負担が軽減され、結果的に屋根全体の劣化が遅くなる傾向があります。 また、軒の長さをしっかり確保していれば、外壁を紫外線や雨から守り、劣化を抑制する効果も期待できます。 寄棟屋根は、日本の伝統的な家屋でも切妻屋根と並んでよく採用されてきました。しかし、大棟と各下り棟を繋ぐ「隅棟(すみむね)」と呼ばれるY字型の部分など、役物(板金など)の接合部が増えるため、そこから雨水が漏れるリスクが他のシンプルな屋根よりは高くなります。このため、これらの部分は定期的なメンテナンスが欠かせません。
雨漏りしにくい建物の条件②:軒(のき)があること
雨漏りに強い建物のデザインを考える上で、「軒(のき)」の有無は非常に重要な要素となります。軒とは、建物において、屋根が外壁や窓、玄関などよりも外側に出っ張っている部分のことを指し、家にとって「傘」や「庇(ひさし)」のような役割を果たしています。
近年は、屋根の出っ張りが少ない、あるいは全くない住宅を「軒ゼロ住宅」と呼び、モダンでスタイリッシュな外観から人気が高まっています。軒のない家は、建築コストが抑えられたり、狭い土地面積を有効に活用した設計が可能になるといったメリットがある一方で、雨漏りのリスクは高まります。
軒のない家は、外壁や窓が雨風の影響をダイレクトに受けるため、雨水が直接外壁に当たりやすく、**サッシ周りや外壁のひび割れ、目地(コーキング)の劣化箇所から雨水が浸入するリスクが高まります。**また、雨漏り以外にも、外壁の汚れがつきやすかったり、太陽光による紫外線や熱の影響を直接受けるため、外壁材や塗膜の劣化が早まるリスクもあります。
雨漏りしにくい建物の条件③:壁面にガルバリウム鋼板を使用
建物の壁面にガルバリウム鋼板を使用した建設は、近年、その優れた耐久性や経済性、そしてスタイリッシュな外観から注目されており、この素材を使用した建物が増えてきています。
ガルバリウム鋼板とは
ガルバリウム鋼板は、鋼板にアルミニウム、亜鉛、シリコンの合金をコーティングした金属素材です。この特殊な合金コーティングが、ガルバリウム鋼板に優れた耐食性(サビにくさ)と耐久性をもたらし、建築材料としての価値を高めています。
一般的な住宅では、壁面に窯業系サイディングボードを使用することが多いですが、サイディングを施工する際には、サイディングボードとサイディングボードの間に必ず「目地(隙間)」が発生します。もちろん、この目地はコーキング材で処理を行いますが、この目地のメンテナンスを怠ると、コーキング材が劣化してひび割れや剥がれが発生し、そこから雨水が浸入する主要な経路となってしまいます。
その点、ガルバリウム鋼板は、屋根や壁面を一枚の大きな板で覆うように施工できるため、サイディングに比べて継ぎ目(目地)を非常に少なくすることが可能です。継ぎ目が少ないほど、雨水が侵入する隙間が減るため、結果として雨漏りのリスクが低減します。
簡単な雨漏りセルフチェック:早期発見のために
どんなに注意して設計・施工された建物でも、経年劣化や予期せぬ要因で雨水が侵入することはありえます。雨漏りが発生しているかどうか、日頃から簡単なセルフチェックを行い、早期発見に努めましょう。
以下の症状が見られたら、雨漏りの可能性があるかもしれません。
- 壁紙に黒いカビが発生していないか?
- 特に天井に近い部分や、窓枠周辺、壁の隅などにカビが見られる場合、内部で湿気が滞留している可能性があります。
- 壁紙にシミが発生していないか?
- 天井や壁に、水が染みたような黄ばんだシミや輪染みがないか確認しましょう。雨が降った後にシミが濃くなる場合は、雨漏りの可能性が高いです。
- 壁紙が凸凹に浮いてきていないか、あるいは剥がれてきていないか?
- 水分の影響で壁紙の裏の接着剤が剥がれたり、壁紙自体が膨らんだりすることがあります。触ってみて、フワフワするようなら注意が必要です。
このような症状が見られたら、ご自身で判断せずに、早めに内装工事業者や防水工事業者、あるいは建物診断の専門業者に相談することを検討してください。
まとめ:デザイン性と機能性のバランスが「良い住まい」の鍵
雨漏りしにくい家という観点から見ると、屋根の形状がシンプルであること、軒(のき)があること、そして外壁材にガルバリウム鋼板のような継ぎ目の少ない素材を使用することなどが挙げられます。これらの要素は、機能性や耐久性を高める上で非常に有効です。
しかし、快適な暮らしという観点では、建物のデザイン性や意匠にこだわることも、居住者や利用者にとって非常に重要な要素です。例えば、軒ゼロ住宅のようなスタイリッシュなデザインは魅力的ですが、雨仕舞いの点ではリスクを伴います。
結局のところ、**デザイン性と機能性、そしてメンテナンス性を考慮し、住む人や利用する人にとってバランスの取れた住宅こそが「良い住まい」**と言えるのではないでしょうか。
株式会社水蔵では、雨漏り調査のご依頼や、建物の防水・外壁に関するご相談を広く受け付けております。お客様の建物の状態やご希望に合わせて、最適な改善策をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 0120-9393-56
0120-9393-56

